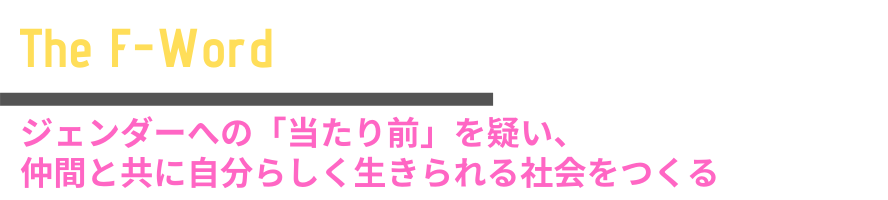以前のブログではカネボウのCMから現代の化粧をすることに対する女性への抑圧について書いたが、化粧が「当たり前にするもの」という認識はいったいどこから来たのだろうか?
現代社会で起こっている当たり前の出来事は、歴史を振り返ると全く「当たり前」ではないことはたくさんある。
日本で女性が選挙権を持ったのもよく考えれば、戦後からで、まだ私たち女性が参政権を持って100年もたっていないのだ。当たり前の権利は、歴史のなかで、他の女性たちが戦って勝ち得てきたものなのだ。
今回ご紹介するのは、Kathy Peiss “Hope in a Jar: The Making of America’s Beauty Culture
(New York: Metropolitan Books, 1998)”という本だ。日本語訳が出ていないので、ぜひ英語の勉強だと思って読んでみてほしいのだが、アメリカ史の中で、化粧に対する社会的概念がどのように変容していったかという歴史書である。
研究書ではありつつも、様々な角度から化粧に対する概念の歴史を描いていてとても読みやすく面白い本である。
テーマとしては、女性のメイクがアイデンティティを隠すためのネガティブな「painting」と呼ばれるものからポジティブな「メイク」へと変化していく中での社会的モダニズムと女性の体験を描いている。
19世紀から20世紀半ばまでの化粧の歴史の変容を、人種、階級、女性のエージェンシーなどを軸に様々な角度から描き、美の文化を単なる商業の一種としてではなく、女性が現代社会のなかで変化していく条件を示すシステムとして理解していく。
化粧が女性にとって有害であると思われていた19世紀後半から、化粧によって女性が公共の場所での発言権を生み出す20世紀の初期、そして化粧品業界が盛んになることで女性の起業家を生み出し、女性の社会的地位を上げることに貢献した20世紀半ばの変容を具体的な例を用いて考察している。
このような歴史的変容を考えると、現代の「化粧は女性だけのものではない」ことや「化粧が社会的マナー」とされていること、「ナチュラリストによる化粧への否定」など、現代社会で起こっていることはこれまでの歴史のなかで起こった変容の一部であり、社会的な変化と繋がっていると考えるとおもしろい。
女性(女性に限らず)が自分自身でエージェンシーを持って、化粧をしていくことが、「化粧をするべき」とされる社会的抑圧の中に取り込まれずに、主体性を持って関わっていくことが大切だなと改めて感じた。